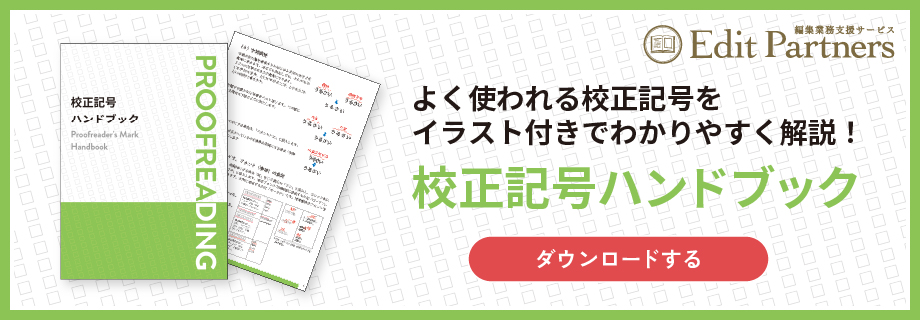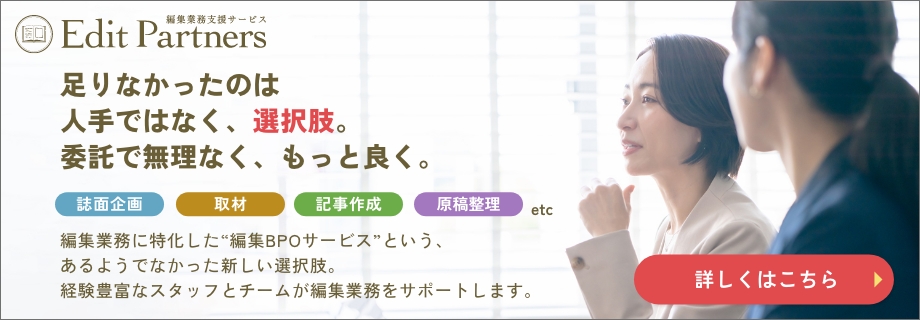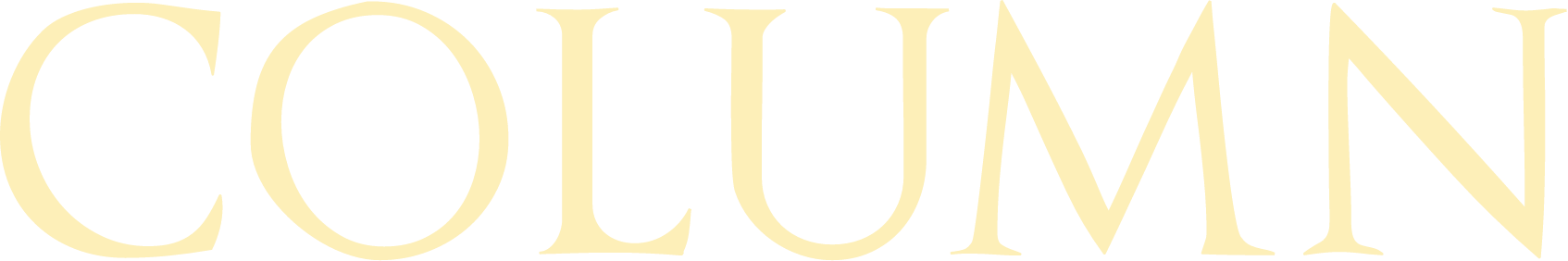記念誌の作り方とは?企画・構成・デザイン・制作の流れと成功のポイント
企業や団体が節目を迎えるときに欠かせない「記念誌」。これまでの歩みをまとめ、社員や関係者への感謝を伝えると同時に、未来へのメッセージを残すことができます。
とはいえ、いざ制作を任されると「どんな構成にすればよいのか」「企画やデザインはどう考えればよいのか」と迷う方も少なくないのではないでしょうか。
そこで本記事では、記念誌の基本構成から企画・内容のアイデア、制作の流れ、成功させるためのポイントまでをわかりやすく解説します。
記念誌とは?その役割と目的
記念誌は「節目の出来事をかたちに残す冊子」として、企業や団体にとって重要な意味を持ちます。単なる歴史の記録にとどまらず、感謝の思いを伝えたり未来へのビジョンを共有したりと、多彩な役割を担うのが特徴です。ここでは、記念誌の基本的な意味や、制作の目的・メリットを整理します。
記念誌の定義
記念誌とは、創立や周年、事業の節目などにあわせて制作される冊子です。過去の出来事を振り返るとともに、そこに関わった人々の思いや成果を「読み物」として表現します。歴史を記録できる点に加えて、記念品としての価値や、未来に向けたメッセージ性を持たせられる点が特徴です。
制作の目的やメリット
記念誌を作ることで得られる効果としては、次のようなものがあります。
・ブランド強化:企業姿勢や価値観を可視化し、社内外にアピールできる。
・社内活性化:インタビューや座談会を通じて、社員同士の一体感を育む。
・記録保存:単なる資料ではなく「後世に残る形」として高い保存価値を持つ。
このように記念誌は、過去を振り返ると同時に、現在や未来を見据える「記録」と「贈り物」の両方の役割を果たすツールといえます。
記念誌の基本構成
記念誌は構成の工夫次第で読者に与える印象が大きく変わります。基本的には「前付け」「本文」「資料編」「後付け」という流れで構成されますが、それぞれのパートに適した企画を盛り込むことで、保存価値と読み物としての魅力が両立します。
1. 前付け:表紙、タイトル、目次、巻頭言
前付けは、記念誌の入口となる部分です。表紙デザインは冊子全体の印象を決めるため、企業カラーや周年数をシンボリックに表現すると効果的です。巻頭には代表や会長の挨拶を配置し、読者に向けたメッセージとしての意味合いを持たせるとよいでしょう。
【企画例】
代表者インタビュー/記念年数を象徴するロゴ・スローガン掲載/歴代建物や商品写真を使ったビジュアルページ
2. 本文:沿革、出来事、エピソード、インタビュー
記念誌の中心を構成するのが本文です。沿革や出来事を時系列で整理するだけでなく、社員や関係者のエピソードを取り入れることで、単なる「記録」から「物語」へと発展させることができます。
【企画例】
創業期から現在までのストーリー/社員やOBの座談会/顧客や地域からの声/成功事例やターニングポイントの紹介
3. 資料編:年表、数値データ、主要取引先、関連写真
資料編では、年表や数値データを体系的に整理し、後世の振り返りに役立つ形に仕上げます。
【企画例】
創業から現在までの年表/売上・従業員数の推移グラフ/主要プロジェクトや製品一覧/関連する新聞記事や資料の転載
4. 後付け:謝辞、奥付、索引
冊子の最後には、協力者への感謝や、編集制作チームのクレジットを掲載します。後付は目立たない部分に見えますが、関わった人々への敬意を示す大切なパートです。
【企画例】
記念誌制作に協力した社員・関係者の一覧/「未来へのメッセージ」コーナー/索引ページで読み返しやすさを強化
記念誌制作の流れ
記念誌は一度作れば長く残るものだからこそ、完成度の高さが求められます。その分、完成までには多くの工程があり、想像以上に時間と手間がかかります。全体の流れを把握せずに着手してしまうと、締め切りに間に合わなかったり、内容が散漫になったりしてしまう恐れもあります。
ここでは、制作をスムーズに進めるための基本的な流れを紹介していきます。
1. 企画・構成案、スケジュールづくり
まず大切なのは、「誰のために、何を伝える記念誌なのか」をはっきりさせることです。社員に向けたメッセージなのか、取引先や地域社会に向けた発信なのかによって、内容や表現は大きく変わります。最初に目的を共有しておくことで、制作途中での迷いや方向性のぶれを防げます。
また、記念誌は周年や式典にあわせて発行するケースが多いため、スケジュール管理は欠かせません。完成から逆算して各工程の期限を設定し、余裕をもって進めることが重要です。特に資料収集やインタビューは予想以上に時間がかかるため、早めの着手を心がけましょう。
この段階でスケジュールを逆算し、キーメッセージを明確にして関係者と合意を取っておくと、後工程での修正を最小限に抑えられます。
2. 資料収集・インタビュー
次に、記念誌に必要な素材を集めます。記念誌の質を左右するのが、写真や資料といった素材です。解像度が低い写真や不足した資料では、誌面の完成度が損なわれてしまいます。社内外の協力を得ながら、できるだけ早い段階から素材を集め、使用許諾やクレジット表記も確認しておくことが重要です。
過去の写真や社内資料、新聞記事などを体系的に整理し、関係者へのインタビューも実施しましょう。
3. 執筆・編集
集めた素材を記事化する際には、事実を並べるだけでなく、読者が感情移入できるストーリー性を意識しましょう。章ごとの分量を整え、全体のトーンを統一することで、読みやすさと完成度が高まります。冗長な部分は削り、見出しや小見出しで流れを整理することも大切です。
また、編集段階では「読み手の立場」でチェックし、初めて読む人にも理解しやすい表現を心がけましょう。
4. デザイン・レイアウト
誌面のデザインは、「読みやすさ」と「記念品らしさ」を両立させることが求められます。ブランドカラーを活かしつつ、写真や図版を効果的に配置し、余白を意識したレイアウトにすることで、統一感のある美しい冊子に仕上がります。
ただし、デザインは凝りすぎると読みにくくなってしまうこともあります。写真や図版を効果的に配置しながら、視覚的な魅力と情報の伝わりやすさをバランスよく整えることで、保存価値の高い一冊になるでしょう。
5. 校正・印刷・製本
原稿が完成したら、誤字脱字や事実関係の誤りを細かくチェックします。複数人で校正することで精度が上がり、見落としを防げます。制作会社とも早めに打ち合わせを行い、紙質や加工方法を検討し、納期から逆算して準備を進めることが大切です。
▼誤字脱字をチェックするコツは、以下の記事で詳しくご紹介しています。あわせて参考にしてみてください。
記念誌制作は「企画から製本までの流れをいかに計画的に進めるか」が成功の鍵です。各ステップを丁寧に管理することで、完成度の高い一冊を効率的に仕上げることができます。
まとめ
記念誌は、過去の歩みを振り返るだけでなく、社員や関係者への感謝を伝え、未来へのメッセージを込められる特別な冊子です。制作の流れを理解し、企画・構成案づくりから資料収集、執筆・編集、デザイン、校正・印刷までを計画的に進めることで、完成度の高い一冊に仕上げることができます。
記念誌は一度制作すれば、世代を超えて読み継がれる組織の財産となります。ぜひ本記事を参考に、構成やデザインに工夫を凝らしながら、自社ならではのストーリーを形にし、世代を超えて価値を持ち続ける一冊を目指してください。